Table of Contents
はじめに
親戚からお祝いをいただくと、嬉しい気持ちと同時に「お返し、どうしよう?」と頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。特に親戚への内祝いやお返しは、金額の相場や贈るタイミング、品物の選び方など、特有のマナーがあって少し複雑に感じますよね。失礼があってはと考えると、余計にプレッシャーを感じてしまうかもしれません。 この記事では、そんな親戚への内祝いやお返しに関する疑問や不安を解消するため、基本的な考え方から具体的な相場、失礼にならないためのマナー、そして相手に心から喜ばれる品物の選び方まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、きっと親戚への内祝いやお返し選びがスムーズに進み、感謝の気持ちをしっかりと伝えられるはずです。さあ、一緒に見ていきましょう。
親戚への内祝いとは?基本を解説
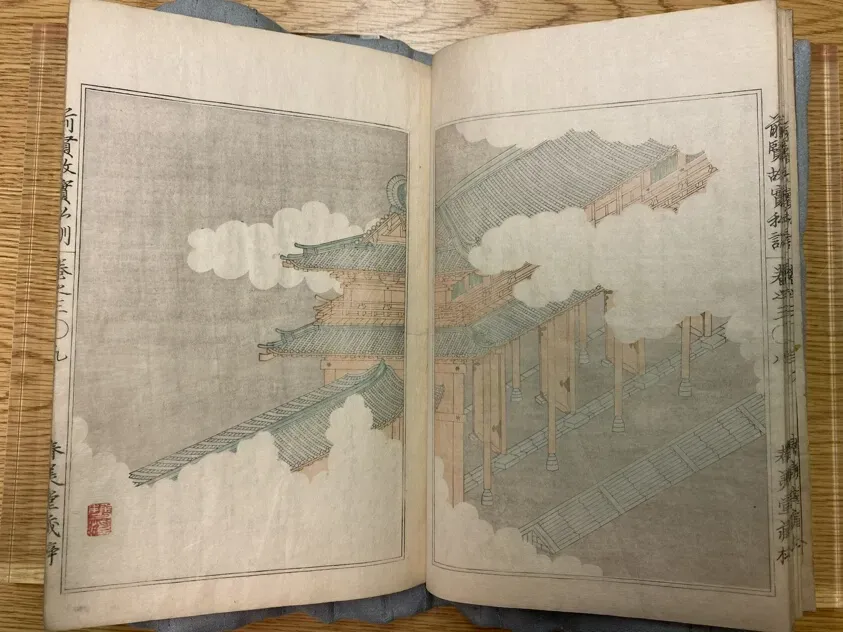
親戚への内祝いとは?基本を解説
内祝いってそもそも何?お返しとどう違うの?
「内祝い」って言葉、よく聞きますよね。でも「お祝いへのお返し」のことでしょう?と思っていませんか?実は、内祝いは本来、お祝いごとがあった家が、その喜びを親しい人たちにお裾分けするという意味合いが強かったんです。
例えば、昔は結婚や出産など、家におめでたいことがあった時に、親戚や近所の人に品物を配って「うちで良いことがありましたよ!」と報告し、一緒に喜んでもらうためのものでした。だから、お祝いをいただいていなくても贈ることもあったんです。
それが時代とともに変化して、今では「いただいたお祝いへのお返し」という意味合いが一般的になりました。特に結婚や出産、新築などの大きなお祝いに対して、感謝の気持ちを込めて贈るのが今の「内祝い」です。だから、「お返し」と考えても間違いではないんですが、元々はちょっと違う意味だった、という豆知識です。
親戚に内祝いを贈るべきシーンって?
親戚へ内祝いを贈るべき主なシーンは、結婚祝い、出産祝い、新築・引越し祝いなど、人生の節目となるお祝いをいただいた時です。
親戚は、家族に近い存在だからこそ、きちんとお礼の気持ちを伝えることが大切になります。特に高額なお祝いをいただいた場合や、遠方で直接お礼を言えない場合などは、内祝いを贈るのが一般的です。
もちろん、「お返しはいらないよ」と言われることもあります。そんな時は、相手の気持ちを尊重しつつ、感謝の気持ちを伝える別の方法を考えるのも良いでしょう。例えば、後日改めて食事をご馳走するなど、形にとらわれすぎずに対応することも大切です。ただ、基本的にはお祝いをいただいたら内祝いを贈る、と覚えておけば間違いないでしょう。
- 結婚祝い
- 出産祝い
- 新築・引越し祝い
- その他、大きなお祝いをいただいた時
親戚の内祝い、相場はいくら?

親戚の内祝い、相場はいくら?
親戚への内祝い、基本的な相場って?
さて、一番気になるのが「結局いくらくらいのものを贈ればいいの?」という相場ですよね。
親戚への内祝いの相場は、いただいたお祝いの金額の「半返し」、つまり半分くらいが一般的とされています。
例えば、1万円のお祝いをいただいたら、5千円程度の内祝いを贈るイメージです。
これはあくまで基本的な考え方ですが、親戚とはいえ、その関係性の深さや年齢によっても少し変わってきたりします。
でも、迷ったらまず「半返し」を基準に考えてみてください。
高額なお祝いや目上の方への内祝い相場
もし、親戚の中でも特にお世話になっている方や、祖父母など目上の方から高額のお祝いをいただいた場合はどうでしょうか。
この場合も基本は半返しですが、あまりに高額だと半返しでもかなりの金額になってしまいますよね。
そんな時は、無理に半返しにこだわらず、3分の1返し程度でも失礼にはあたらないという考え方もあります。
大切なのは金額そのものよりも、感謝の気持ちを伝えることです。
ただし、あまりに少なすぎるとかえって失礼になることもあるので、加減が難しいところです。
いただいたお祝いの金額 | 内祝いの目安(半返し) |
|---|---|
5,000円 | 2,500円程度 |
10,000円 | 5,000円程度 |
30,000円 | 15,000円程度 |
50,000円 | 25,000円程度 |
100,000円 | 30,000円~50,000円程度 |
相場以外で考慮すること
親戚への内祝いの相場はあくまで目安です。
中には「お返しは本当にいらないからね!」と強くおっしゃる方もいます。
そんな時は、無理に高額なものを贈るより、感謝の気持ちを丁寧にお伝えし、菓子折りなど気持ちばかりの品を贈るか、落ち着いてから食事に招待するなどしても良いでしょう。
また、親戚間で内祝いの習慣や相場感が異なる場合もあります。
心配であれば、両親や他の親戚にそれとなく相談してみるのも一つの手です。
地域や家ごとの慣習も考慮に入れると、よりスムーズに進むことが多いですよ。
親戚へ内祝いを贈る際のマナー
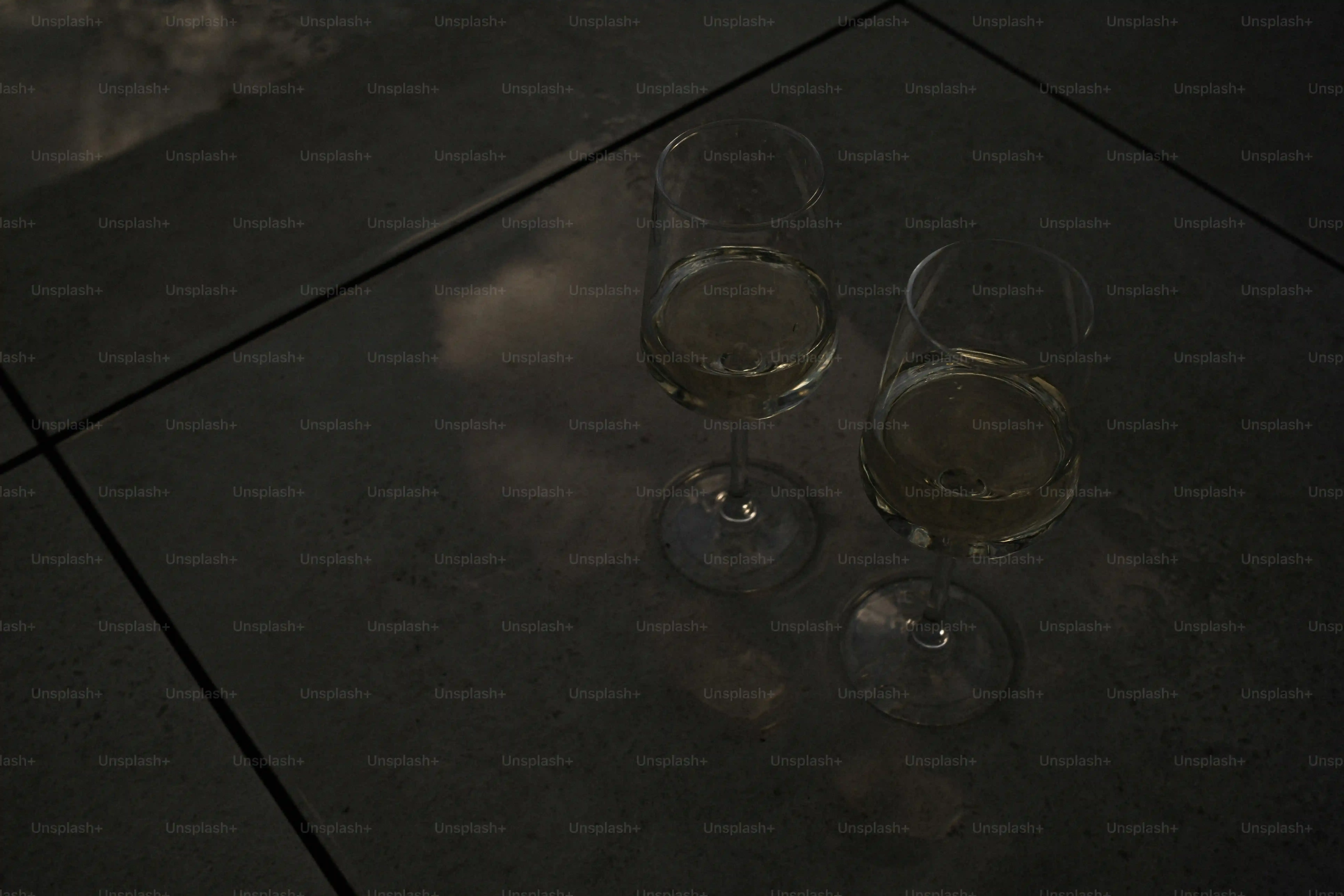
親戚へ内祝いを贈る際のマナー
いつ贈るのが正解?内祝いのタイミング
親戚への内祝い、いつ贈るのがベストタイミングかご存知ですか?実はこれ、けっこう重要なんです。
基本的には、お祝いをいただいてから「1ヶ月以内」に贈るのがマナーとされています。
結婚内祝いなら結婚式後1ヶ月以内、出産内祝いなら赤ちゃんのお宮参りの頃(生後1ヶ月頃)が目安ですね。
遅すぎると「あれ?忘れられてる?」なんて思われかねません。
早すぎるのもちょっと性急な印象を与えることも。
まあ、最近はそこまで厳格じゃないですが、目安として覚えておくと安心です。
もし、うっかり1ヶ月を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点ですぐに準備して、遅くなったお詫びの言葉を添えて贈りましょう。
正直に「遅くなってしまって申し訳ありません」と伝える方が、かえって誠意が伝わったりしますよ。
- 結婚内祝い:結婚式後1ヶ月以内が目安
- 出産内祝い:生後1ヶ月頃(お宮参りの時期)が目安
- 新築・引越し内祝い:引越し後1~2ヶ月以内が目安
- 快気祝い(病気回復のお祝い):退院後10日~1ヶ月以内が目安
贈り方と添えるメッセージの心遣い
品物が決まったら、どうやって親戚に届けるか。
直接手渡しできれば一番丁寧ですが、遠方だったり忙しかったりする場合は配送が一般的です。
配送する際は、ただ送るだけでなく、ぜひ「お礼状」や「メッセージカード」を添えてください。
これが、内祝いの品物と同じくらい、いやそれ以上に気持ちが伝わる大切な要素なんです。
「この度は素敵なお祝いをありがとうございました。ささやかですが、感謝の気持ちです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」といった、シンプルでも感謝の気持ちが伝わる言葉を選びましょう。
品物には紅白の「熨斗(のし)」をつけるのが基本マナー。
結婚なら結び切り、出産なら蝶結びなど、用途に合わせた水引を選びましょう。
どんな品物を選ぶにしても、心を込めて準備することが一番大切です。
親戚に喜ばれる内祝いのお返し選び

親戚に喜ばれる内祝いのお返し選び
「これなら間違いない」親戚に贈る定番ギフト
さて、いよいよ品物選びですね。親戚への内祝いのお返し、何を選べばいいか迷いますよね。
失敗したくない、でもありきたりすぎるのもつまらない。そんな時に頼りになるのが、やっぱり定番のギフトです。
例えば、上質なタオルセットやお菓子、飲み物などは、誰にでも喜ばれやすく、いくつあっても困らない鉄板アイテム。
特に、自分ではなかなか買わないような、ちょっと高級感のあるものを選ぶと「おっ、良いものもらったな」と思ってもらえます。
実用性があって、かつ少し特別感があるものが、親戚への内祝いとしては喜ばれる傾向にありますね。
相手の年齢や家族構成を考慮して、普段使いできるものや、みんなで楽しめるものを選ぶと、より感謝の気持ちが伝わりやすいでしょう。
相手の「好き」を贈るなら?+αの選び方
定番も良いけれど、せっかくだから相手が本当に好きなものを贈って驚かせたい!そう思うなら、少しリサーチが必要です。
親戚の趣味や好みを事前に聞いてみるのが一番ですが、難しければ、両親や他の親戚にそれとなく聞いてみるのも有効な手段です。
例えば、お酒が好きならちょっと珍しい日本酒やワイン、コーヒーが好きならこだわりの豆など。
最近は、特定の地域の特産品や、話題になっているスイーツなども人気があります。
また、相手に選ぶ楽しみを贈るという意味で、カタログギフトも有力な選択肢の一つです。
特に親戚が多い場合や、好みが分からない場合には、カタログギフトは非常に便利で、贈る側も受け取る側も負担が少ないかもしれません。
meowjapan.asiaでも、内祝いにぴったりなギフトを多数取り扱っているので、ぜひ覗いてみてください。
- 高級感のあるタオルや雑貨
- 有名ブランドや老舗の菓子折り
- 高品質なコーヒー、紅茶、日本茶
- 調味料や油など、少し特別な食品
- 相手の好みに合わせたお酒
- 選ぶ楽しみがあるカタログギフト
親戚への感謝を形に
親戚への内祝いやお返しは、単にお祝いへのお礼というだけでなく、これからも良好な関係を続けていきたいという気持ちを伝える大切な機会です。相場やマナーを守りつつ、相手の顔を思い浮かべながら品物を選ぶ時間は、きっと感謝の気持ちを再確認させてくれるでしょう。この記事が、あなたの内祝い・お返し選びの一助となれば幸いです。心を込めて選んだ贈り物は、きっと相手に喜ばれ、家族の絆をより一層深めるきっかけになるはずです。